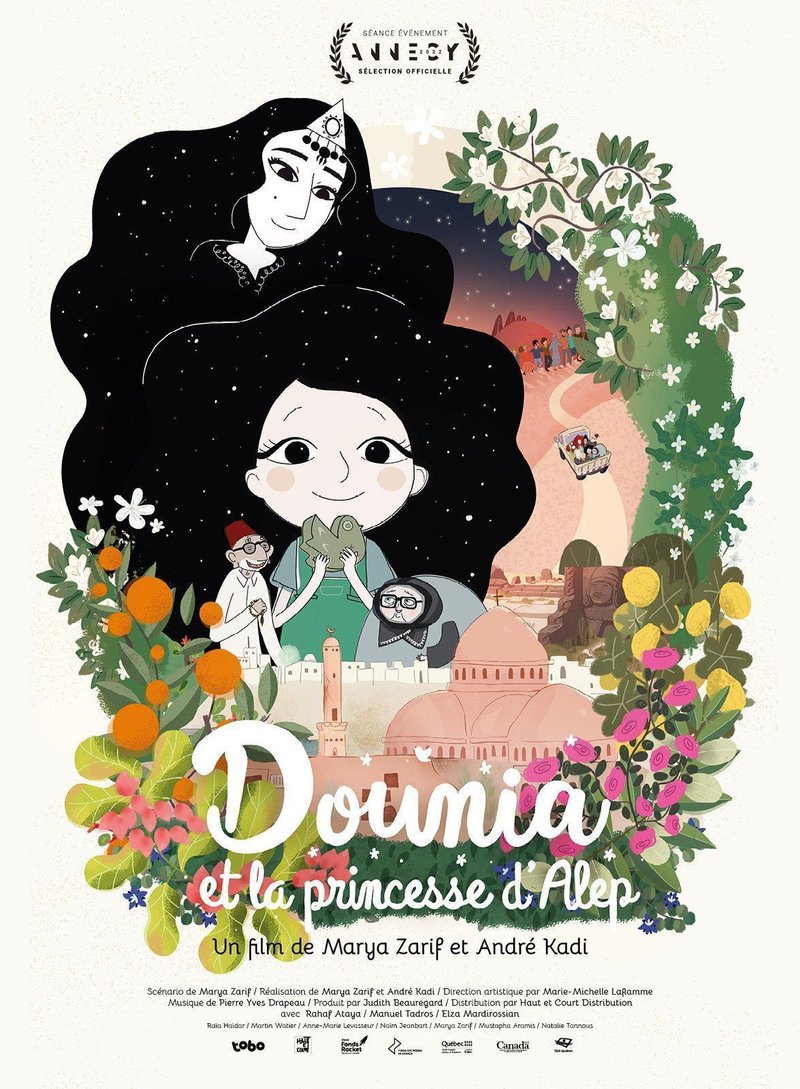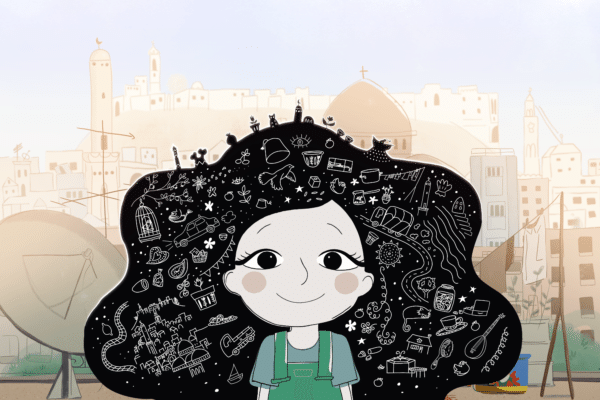「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」
新年一発目がこれ、というのは我ながらどうかとおもうのだけれどタダで観れるなら見るに越したことはあるまいて。新作も今年やるみたいだし。
とはいえ、私は熱心なまどマギファンではないし、当時はそこまで熱心にアニメを追っているわけではなかった(そうだったら公開当時に観てるし)。一応、テレビ版の本放送をリアルタイムで追ってはいたので当時の震災を含めたある種の時代性を帯びたことによる熱狂はある程度知ってはいたのだけれど、逆に言えばそれ以降の劇場版総集編や雨後の筍のように湧いて出た批評の数々にまったく触れていなかったし、ヒットした作品の常としての澎湃として生じた数々のパブにも触れていなかった。
この間ようやっと当時のユリイカの特集を買ったくらい(まだ読んでない)なので、そういう意味ではまどマギ弱者であることは否めない。
しかしそんな弱者から見ても新編は面白かった。まずもって久方ぶりの犬カレー空間の異様さやカット数の多さなど、劇場版アニメにしてもその情報量の多さはちょっと異常である。まどマギはそれこそアニメバブル前夜の時代ということもあって興行収入こそ今のアニメ全盛の状況と比べると少し見劣りする(それでも20億超えてるので十分)が、作風的にもやはり濃ゆいファンがいるのでウィキも充実している。で、それを頼りにするとやはり絵コンテで2300カットあるとかで、まあそれだけカメラ位置を調整しているということである。
ただキャラクターが喋るだけで3カメ使ったり、アクションつなぎだったりアニメでそれをやるとなるとその分だけ新しい場面の絵を描かなければならないので手間になるはずなのですが、まあシャフトの場合は純粋な動性のあるアニメーションというよりは静的な動きの少ないカットの連続で見せていくところがあるので、アニメーションとしてはミニマルな手法のそれを手数を増やして贅沢にやるというちょっと面白いことをやっている気がする。
といいつつも戦闘シーン(ザ・ワールド)や変身シーンの手の込みよう(保守本流の魔法少女変身シーンを脱臼させBGMもどこか不穏な装いがある)は、そういうミニマリズムとは別の映像的快楽をもたらしてくれる。
まあ要するに映像だけを取り出しても十分面白いということではある。後半のジャーゴンじみた用語の連続も、別にしっかりと理解する必要はなくて(その気があるなら映像はもっと抑えるだろう)、むしろそういったきっかりとしたSF的な説明の粗さを煙に巻くところがある。
何せ掲げられるお題目が「愛」である。いやもちろんSFの中で愛はヒューマニズムの観点からなどもよく取り上げられるものではあるけれど、それを宇宙の法則を書き換えるほどのエネルギーの源泉として扱うとなればもはやSF的なセンスオブワンダーで語るにはあまりにも大文字の「愛」過ぎるので、要するに「こまけぇこたぁいんだよ。愛だよ愛、最後に愛は勝つ」という本作のというかまどマギのテーマの全面展開のための方便なのだ。
マギレコの方はやってないしアニメも見てないのでアレが「まどマギ」とどういう位置づけなのか分からないんですけど、少なくとも2024年の新作が発表されるまでは本作が(とりあえずの)正当続編という扱いではあったと考えると、本作は実質的に「まどマギ」におけるメリーバッドエンドであると言えるのだがQBザマァエンドではあったので(しかしそのラストカットのQBの顔こそが「バッド」を予期させるのだが)個人的にはグッドエンドであった。
という冗談はさておき、テレビシリーズはいわばまどかの救済の話だったと思うのだけれど、この新編はほむらの(自力)救済の話でござんしょ。
どちらも実質的な主人公はほむらであるということにそこまで異論は生じないと思う。しかし、ここで個人的な所感を述べさせてもらえば、そういった一般論を差し引いたとしても「まどか」という存在が奇妙に映る。テレビシリーズの記憶が曖昧だもんで単に忘れているということもあるかもしれないんですが、「まどか」に対する印象がほとんどないのです、私。
いや「まどマギ」と言われて真っ先に思い浮かぶ顔はまどかだし、決して空気とかそういうことがいいたいわけではない。むしろ、それよりももっと大きな枠組みとしての「空虚」という言葉で表すべきキャラクターではあるかもしれない。
まどマギにおけるまどかは、その存在がほとんど舞台装置的といっていい(ワルプルギスの夜が舞台装置の魔女と呼ばれているのを初めて知ったんですけど、これも犬カレー背景や劇中の「幕間」の演出を観ると意味深)。おもえばテレビシリーズにおいても、物語を牽引するのはまどかではなくその周囲の魔法少女たちだったし、彼女らが魔法少女になるための願い、願うに至ったバックグラウンドもしっかりと描かれている。
そう考えると、ほかの魔法少女たちには家庭や家族といったものが(私のおぼろげな記憶の範囲では)描かれないのに対し(設定的にはさやかやほむらの家族は存在していてもおかしくないはずなので)、まどかには極めて通俗的な「充足した」家族が描かれることも奇妙に映る。多くのアニメにおける少年少女に家族が描かれないのは、むしろそれが彼女たちのキャラにとってノイズになりえるからで、キャラとして強ければむしろ不必要ですらあり(あるいは事前に設定レベルから排除されている)、なればこそまどか以外の魔法少女たちにはそのような存在を必要としない強度が与えられていると逆説的にいえる。
しかしまどかには家族が描かれる。
それはまどかの「キャラの弱さ」を虚飾すると同時に書割的に描かれる「幸福な家族像」によって、より一層まどかの空虚さを補填しているように見える。
創作物においてすでに満たされているキャラクターほど退屈なものはないだろう。何せ満たされているのであれば「何かをなそう」とする行動原理が生じえないのだから。せいぜいが「現状維持」だ。もっとも、その「現状維持」がある意味では本作の物事の重要な願望ではあるし、それを突き詰めると「ループ」という無限性に突入するので、そういう意味ではまどかのそれはやはり重要な要素ではあったのだろう。
ともあれ、テレビシリーズにおけるまどかは魔法少女に憧れこそすれ、そのための願いを持つことがなくモチベーションそのものを終盤まで欠いていた。
しかし、空虚であるということは、ハリウッドの往年のスターがそうであったように大衆の願望の眼差しの器として機能する。空虚で空っぽであるがゆえにあらゆるものを受け止める器になりえるのだ。
やがて「まどか」という存在は「ほむら」の願望の器もとい対象そのものになり、ループによって幾度ももほむらの願望を眼差された結果、「まどか」は空虚なキャラクターであるがゆえの超越性を獲得するにいたる。
他の魔法少女たちが「キャラ」として強かったのは、願いを含めそのキャラクター造形が人間的で魅力的であったからだ。翻って、キャラとして弱いまどかが魔法少女になるために最終的に掴み取った願いというのは「すべての魔法少女を救いたい(だったはず。多分)」という、人「並み」の願いではないものだった。
それは究極の利他であり、ほかの魔法少女たちが(見かけはともかく)本質的に自己救済的を目的とした「願い」であったのに対して、それは願いというよりもほとんど「祈り」に近いものだった。劇中でもマミがさやかに「他人のために願いを使うのはやばい」みたいなことを言っていたのは、さやかの末路だけではなく、むしろまどかの末路を指していたのではないかと思える。
これは別にそこまで突飛な話ではなくて、なぜならまどかは最終的に円環の理と呼ばれるシステムそのもの(通称アルティメットまどか)になるわけで、まどかという存在が最初からそういうシステム=まどマギ世界を成り立たせる舞台装置であったと考えるのはむしろ自然なことだ。
だから空虚な存在としてのまどかは最終的に(魔法少女≒魔女)を救済するシステムそものとして完成する。
アルティメットまどかに女神あるいは聖母のイメージが付与されているのも、それらの概念が機能としての救済(的存在を内包・産出する)を有しているからだ。
「まどマギ」においてキャラの弱いまどかがそれにもかかわらず「まどマギ」の顔として強烈に印象付けられるのも、その世界のシステムそのものを象る枠であるからだろう。まどかがいなくてもあの世界は存在するが、彼女がいなければほかの魔法少女は輝けない。
近年の例で、より分かりやすくかみ砕かれた例で言えば「グリッドマンユニバース」におけるグリッドマンが割と近いものである気がするが、あそこまで単純明快な感じではない。
テレビの続編としての本作では、書き換えられ完成したシステムとしてのアルティメットまどかから「キャラ」としての「まどか」をほむらが奪掠する話であり、端的に言ってテレビシリーズの結末をひっくり返すとは言わないまでも、中指おったてた結末ではあるはずだ。
それが悪徳として、というと語弊があるので自己中心的な行為として受け止められるのは、ほむらにとっての夢の街を、そのまま世界そのもの、宇宙そのものへと敷衍してしまったから、すなわち自分の掌握可能な箱庭化するということにほかならないからだ。それは徹頭徹尾「利他」のためのに世界を書き換えたまどかとは違い、まどかと一緒にいたいという「利己」のために世界を書き換えたからと言える。
しかし、それは紛れもない、ほむらの人間性の発露でもあり、本質的に魔法少女の「願い」と何ら変わるところはない。
と、ここまで書いてきてこれ以上ディグるのは面倒というか疲れたのでここで切り上げる。
正直キャラクターに対する考察とかは散々されてるので今更私が個別のキャラをどうこういうことはない(杏子とさやかが一番グッとくるということくらいを言及するにとどめる)。だからこそこういうちょっとしたメタでしか語れないんだけれど、まあ書いたような「利己主義」としての「願い」(ほむら)と「利他主義」としての「祈り」(まどか)をどう揚棄するのかは気になるところである。というところでひとまず次作を待つ。
一つ一つのディティールを取り上げてやいのやいの語るのも一興ではあるんですが、そういうのはまあ濃度の濃いまどマギオタに譲るべきでせう。
しいて言えば魔女同士の対決は熱かったですな。魔女として葬られたさやかとなぎさが、なればこそほむらを相克しえるという巨大魔女の衝突の絵面。まあ、概念的スケールの差で最終的にいなされてしまうんだけど、作り変えられた世界でも明確に悪魔としてのほむらを意識できるという可能性はまだ残っているような描き方なのでセーフ(何が)。そのあとのまどかも含めてエネルギー回収システムとしての「魔女」がまだ機能してしまう可能性を保持しているということではあるんですが。
ただまあ、しいて言えば今の目線で考えるとQBの声優はゴリゴリのマッチョを想起させる男性声優の方が、今の目線で観るとよかったんじゃないかと思ったりもするんですよねぇ。そんなチープなエクスキューズはいらんわい、という声も無きにしも非ずではあろうけれど、しかし今やフェミニズム要素なしで魔女(Include魔法少女)を語るのは片手落ち(あんまこの言葉はどうかと思うが)でございますし、ボロ雑巾QBの絵面もマッチョ男性声優だったらよりザマァ感が増したのではないかと思う。
QBといえば次回作ではQBが感情を獲得して対立からの融和路線とか考えたんですけど、まあないよな。
「映画 ギヴン」
テレビでやってたから何の気なしに観たのだが原作もテレビシリーズの方も全くのノータッチ。だもんで、BLアニメであるということをまったく知らず音楽要素が少ない(全く足りてない、ということではなく)上にほとんどが隠喩として機能させられているのでちょっと面食らった。ていうかこれ前後篇の前編なのかよ。二人の物語としてはかなり綺麗にまとまったと思うんだけど次どうすんの。真冬と立夏か。テレビシリーズ観てないとこの二人にスポット当てた場合かなり音楽要素強めになりそうだけど、どうなんだろう。
しかし、割と個人的には好みではあった。いや湿度高すぎてちょっと笑ったりとか最後の告白を言葉として言わせるのはまあ、なんというか女性的というか「言わなきゃ伝わらない」という至極真っ当なディスコミュニケーションの回避を行っているあたりの社会性を感じさせるのだけれど、自分の趣味としては粋じゃない気がした。ていうか共感性羞恥に近い。
いや、雨月と秋彦の告白シーンがどうだったのか(そもそもあったのか)知らないんですけど、プレイバックになってたりしないのかとかね。ていうかアンタらの話がメインなのかよ、とまったくこのコンテンツを知らない身からすると割と衝撃だったのだが。春樹ってメインの中でも割とサイドよりじゃないですか明らかに(失礼)。そういうキャラは好きですけどね、幽遊白書の四人で一番好きなの桑原ですし、私。
そのラストはさておくとして、この映画というか「ギヴン」というのは、少なくともこの映画においては音楽についての映画ではない。秋彦が「音楽の楽しさ」を再び取り戻すという構成ではあり、それは要するにテニプリにおける天衣無縫的なアレなのだが、音楽が音楽そのものではなく「恋愛」というレイヤーと重畳させられていることによって「純粋に音楽が楽しい」という部分に「恋愛」という不純物が紛れ込んでいるように一見すると見える。
というか、実際に「音楽の楽しさ」や「才能との葛藤」という問題系は「恋愛」という強力なテーマによって回収されてしまっているのは否めない。たとえば春樹の「ほかのバンドメンバーに対して才能のない自分」という葛藤は、結局のところそれと並列される秋彦への恋慕と最終的に秋彦がその想いに応じるという形によって問題の本質を穿つことなく慰撫されてしまっている。
ある種の弁証法なのではないかと考えられなくもないかもしれないが、それをやろうとするとかなりダイナミックな飛躍が必要な気も。
音楽と恋愛が重ね合わされているというのは、言うまでもなく劇中のメタファーからも読み取れる。秋彦にとっての恋愛の問題系はその対象としての雨月とヴァイオリン(という過去)に象徴される。それに対置されるのが春樹とドラム(という現在)だ。
雨月=ヴァイオリン(過去):春樹=ベース(現在)の同質的な対置がなされているのだが、秋彦が扱う楽器をそれぞれの時系列と合わせると秋彦(過去)=ヴァイオリン・秋彦(現在)=ドラムなのだ。
ここに秋彦の恋愛における視点・立場の相違がみられる。雨月との過去の恋愛においては、彼と同じ楽器を扱うという営為がそのまま秋彦の同期・同化の願望として反映される。しかし、雨月との間に隔絶した才能の差を感じ取り、それが恋愛に亀裂を生じさせる。
女性にイラマチオさせてるっぽいし雨月に対しても春樹に対しても上位に組伏しているので秋彦はタチもとい攻めだと思うのだが……そこに伴う暴力性は一種のジャイアニズムでありそれが性的・恋愛的な秋彦の志向としてコードを読み取れる。すでに述べたように雨月に対しては彼のヴァイオリンの才能によってそのジャイアニズムが挫折させられ彼との恋が上手くいかなくなる。
攻めは本質的に受けの略取による合一を志向する型と捉えられるので能動的・加虐性を帯びるのだが、そこに「才能の差」と言うノイズを紛れ込ませることで雨月はそれを無効化…あるいは本人の意志の寄らぬ拒絶に繋がる。もちろん、それでも秋彦は無理やりやることもできるが、劇中の描写の限りではそれはない。そう考えるとそれこそが彼の音楽に対する真摯さとして受け止められる。だらしないけど。
いやまあ、そのフラストレーションの対象に春樹が搾取されてしまっているのだが、逆に言えばその真摯さ(ゆえに生じる葛藤)というクソデカ感情を向けられるのが春樹ということでもあり、それはとりもなおさず秋彦が雨月=過去から春樹=現在にその感情のベクトルを変え始めた証でもある。
途中が長くなってしまったが、言いたいのは秋彦の過去性の恋愛は雨月との同質化(ヴァイオリン同士)を望んだことで挫折したのだということ。磁石の極性みたいなもんです。
翻って現在の恋愛性としての春樹がベースなのに対し、秋彦はドラムである。二人が違う楽器を扱っていることに意味があり、そしてその蓋然性の高さを担保するのが「バンド」という形式なのだ。バンドは基本的にメンバーが異なる楽器を担当しなければならない。つまり、バンドメンバーとなった現在の秋彦はかつての独りよがりなヴァイオリンとヴァイオリンという合一のカタチではない相補性を獲得するに至り、それが彼の恋愛的志向にも変化を与えたのだろう。
加えて秋彦と春樹には(両者の間にも差はあれど)「才能を持たざる者」の共通点がある。春樹は秋彦をして「器用貧乏」と評するが、観客からはそれはむしろ(ほかのバンドのサポートに入ったり)春樹にこそ当てはまるように見えるし、実際に彼は秋彦にとっての当事者性を持っていないがゆえに見えるものあり、現に秋彦も同様の評価を春樹に対して行っていた。
それをメタファーとして示すのが花火のシーンだ。春樹のマンションに居候することになった秋彦が、彼と二人で春樹のマンションから花火を見るシーンのセリフで、秋彦は前の場所(雨月と暮らしていた半地下っぽい場所)では見えなかったと述べる。それは逆説的にいえば春樹と同じ視点に立つことで秋彦はそれまで見えていなかったものが見えるようになったということだ。ここにおいて秋彦は完全に雨月(過去)ではなく春樹(現在)と同じ立ち位置を獲得したことが示される。
このように相補的・異質的でありながら同質性を持つ二人(というか秋彦)の恋愛は、バンドという社会性を持った形態を経由し、演奏という営為(によって真冬の才覚に当てられることで、自分とは「似て《音楽》非なる《楽器》」ものを受け入れる)を通じて雨月という過去とけじめをつけて成就する。途中で秋彦がやらかしたりもしたけど。
しかしそれは過去との決別ではない。
細かい部分ではヴァイオリンに対してベースと言う弦楽器(でけぇ括りだけど)であることだが、これは過去性との係累である。劇中の直接的な作劇(秋彦がヴァイオリンを再開したこと)ことからも明白ではあるのだが、そういう部分からも彼が過去を清算・切り捨てたのではなくまさに受容したのだとわかる。
とはいえやはり「恋愛」と「音楽を楽しむ気持ち」を同じ位相で語るのは無茶だったと思う。実際、恋愛の方はともかく音楽の楽しさ・才能の問題はなあなあだし。
またこの映画では各キャラクターのモノローグによるポリフォニー(ホモフォニーではないのがミソ)で補完されているのだが、立夏だけそれがないしその上、出番もないので初見の自分にはキャラがつかめなかった。才能がある側ということはわかるし、それを言えば明らかに主人公である真冬もキーパーソンではありながら出番は少ないので、もしかしたら後編では二人にスポットが当たる構成になっているのかもしれない。
そのおかげか、高校生の二人は恋愛ドロドロ劇場を演じていた秋と春に比べて音楽に対してピュアなキャラとして描かれている。というか描かれていないからこそ、そう受け止められるというか。
そして後編でこそ才能を巡る話になる……のか?分からないけどそうしないとぶち上げた問題が棚上げになってるしなぁ。いや恋愛も面白かったけど。
以下覚書
・名前の法則性は「500日のサマー」っぽい
・秋彦は人好きのするクズ
・地味に音響凝ってる
「リズと青い鳥」
個人的に苦手な監督、山田尚子の監督作なんですが、今回はかなり良かったと思う。これ、後から知ったんですけどユーフォニアムのスピンオフ的続編なんですな。まあ知らずに観たけど全然この一作で完結しているので問題ないのですが。
牛尾さんの音楽もさることながら全体的なサウンドデザインがよろしい。音楽をテーマにした作品は「ギヴン」もそうだったけど、劇伴以外でもその辺を気を遣うっていることが多いと感じるのだけれど、アバンまでの編集のテンポや(ある種の激重感情矢印のミスリード含め)足音などのSE一つ一つの繊細さ、それとこれは山田尚子個人というよりは京アニの色だと思うのだけれど、キャラクターの髪の毛が良い。こういう書き方をすると問題がありそうだけれど、女性監督の場合はキャラクターの髪の毛をかなり丁寧に描くことが多い気がして、それは戯画化されたアホ毛とは違う枝毛じみた毛髪の浮き上がりなどが際立つ。
アバンの廊下を歩くだけのシーンにおける静謐な音や前述の髪の毛を筆頭とした繊細な描写だけでかなり満足。
「聲の形」や「平家物語」の共依存を前提にした対象を神格化することによる贖罪はうげぇと思って観ていたのだけど、「リズと青い鳥」に関してはその辺のバランスが上手く青春時代の一幕として閉じれていたと思う。
近いタイミングで観てしまった「ギヴン」が同じく音楽とその才能の差異を扱っていたのと似て、こちらも似たようなテーマを掲げながらもそこには恋慕というそのほかの事柄をすべて置き去りにしてドライブしてしまう要素がないため、ああいったドロドロ展開にはならない。
冒頭とラストの対比、違う場所を目指しつつも同じ道を歩むということの開かれ具合はグッド。
まあそもそも才能以前に楽器に対する真摯さがダンチなんですよね2人は。かたや腕時計しながら演奏、かたや大事な指を傷つけないために体育の授業に参加しないという徹底ぶり(バスケだしなぁ)
派手さはないけど編集やカメラワークの妙でしっかりとキャラクターの内面が描写されていて、深夜アニメばかり見ているとこういうちゃんとした(アニメ)映画を観るだけですごい快感が。
絵本パートはなんかこう、全体的に(まあ絵本だから当然なんだけど)戯画化されていて、素人吹き替え感も相まってどことなくジブリ臭がしてちょっと笑っちゃいましたけど。
「劇場版 響け!ユーフォニアム〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜」
構成ばりウマ…。最初と最後で金賞と涙の意味が反転するの上手すぎ。